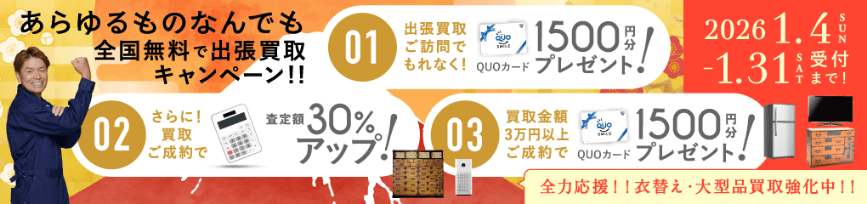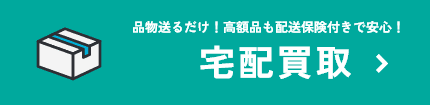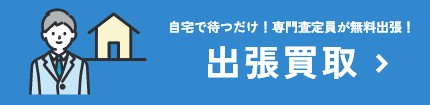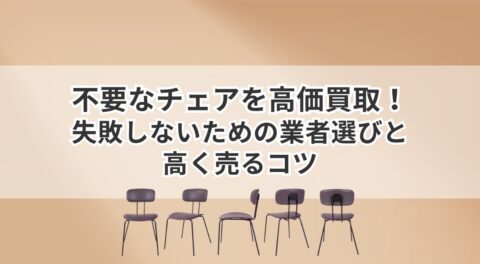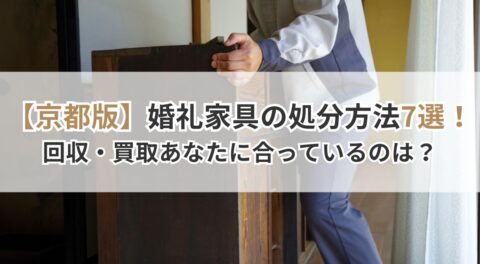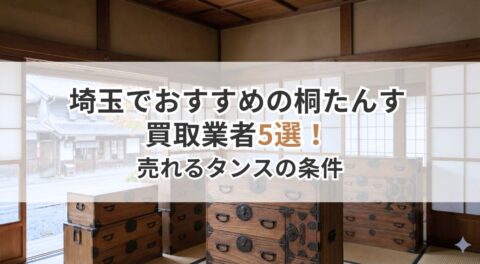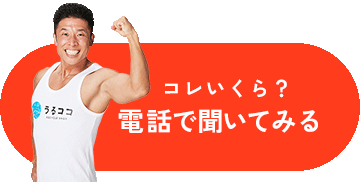桐たんすのカビ、自分で取れる?進行度ごとの対策と買取など別の選択肢も紹介
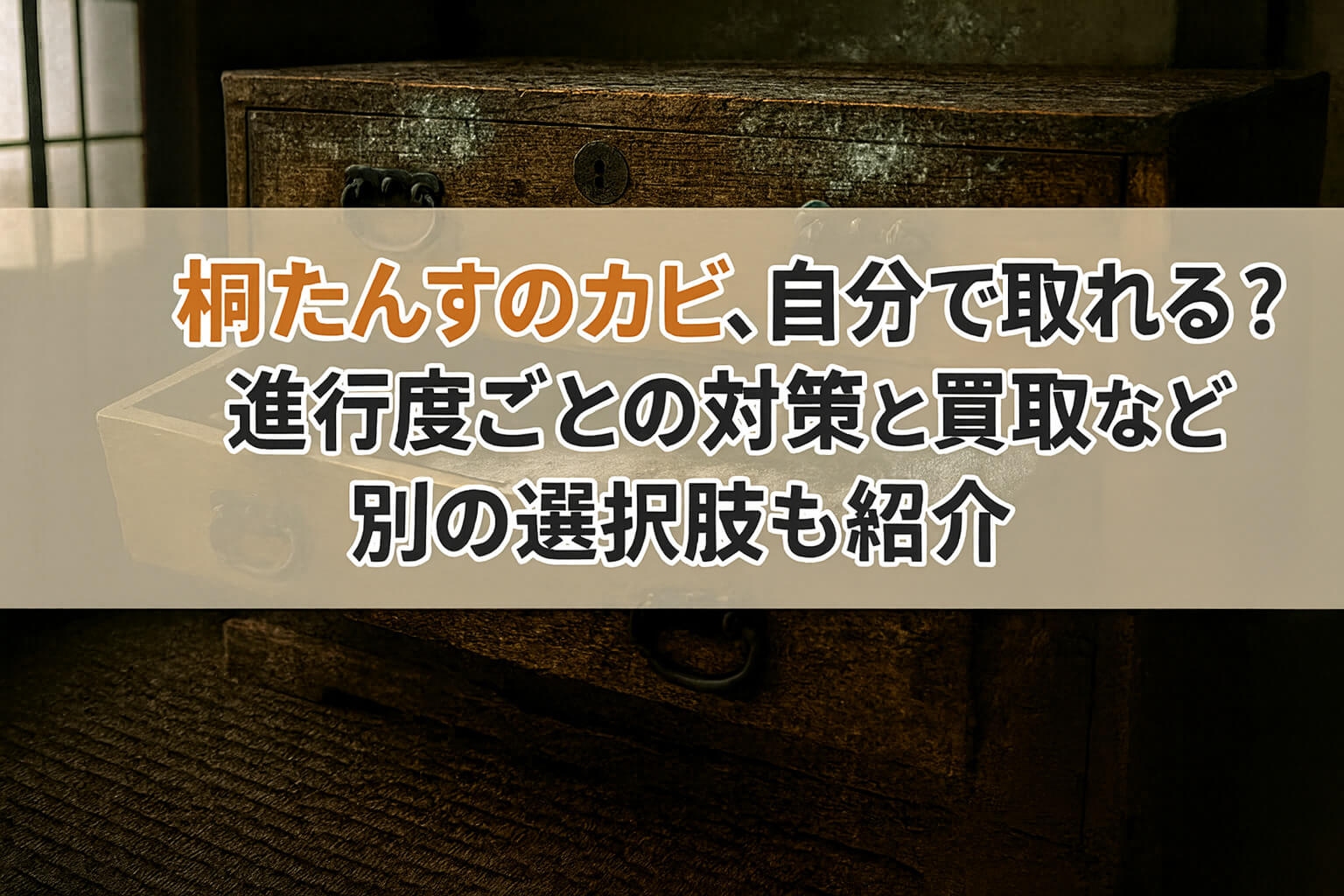
大切な桐たんすにカビを見つけると、ショックでどうすれば良いか迷ってしまうかもしれません。日本の多湿な環境では、日頃のお手入れや設置場所が原因で、桐たんすにカビが生えてしまうことがあります。
この記事では、自分でできる乾拭きを中心とした軽度のカビの対処法から、菌が内部まで侵食したプロに相談すべき中度〜重度の状態まで、見極め方を詳しく解説します。
また、カビ取り後のたんすをリメイクして使い続けたり、専門業者に買い取ってもらったりするなど、今後の活用法についてもご紹介 。あなたの桐たんすの状態に合わせた、最善の選択を見つけるためにお役立てください。
桐たんすにカビが生える原因

桐たんすは本来、調湿性に優れた家具として着物の保管に最適です。しかし、湿度の高い環境や不十分なお手入れ、設置場所の条件などが重なるとカビが発生してしまいます。ここでは、代表的な原因を分かりやすく解説します。
湿気が多い
カビが発生する最大の原因は、言うまでもなく湿気です。カビは気温20〜30℃、湿度60%以上の環境を好み、特に日本では梅雨や秋雨、夏場の高温多湿な時期に活動が活発になります。こうした環境は、桐たんすにとって非常に過酷な状況といえるでしょう。
桐は、湿気が多い時には水分を吸い込み、乾燥すると水分を放出することで、たんす内部の湿度を一定に保つ優れた性質を持っています。しかし、その調湿能力にも限界があります。
常に高い湿度にさらされ続けると、桐自体が水分を過剰に溜め込んでしまい、かえってカビの温床となってしまうのです。
桐たんすをカビから守るためには、部屋の湿度管理が欠かせません。晴れた日には窓を開けて空気を入れ替えたり、除湿器やエアコンのドライ機能を活用したりして、たんすの周りが常に多湿な状態にならないよう心がけましょう。
お手入れ不足
桐たんすを長年お手入れせずに放置してしまうことも、カビを発生させる大きな原因となります。たんすの表面に積もったホコリや、開け閉めの際に付着した手垢などは、湿気を吸着し、カビの栄養源となってしまうからです。
効果的なお手入れは、決して難しいものではありません。月に一度でも、乾いた柔らかい布でたんすの表面を優しく拭き、ホコリを取り除くだけで大きな違いが生まれます。その際には引き出しを少し開けて、内部の空気を入れ替える習慣をつけると、さらに湿気がこもりにくくなり効果的です。
長期間使わない引き出しも、年に数回は中身を確認し、風を通すことが大切です。こうした定期的なチェックを怠ると、カビの初期症状を見逃し、気づいた時には広範囲に広がってしまうことにもなりかねません。
設置場所の通気性が悪い
桐たんすの設置でやりがちなのが、たんすの背面を壁にぴったりとつけてしまうことです。これではたんすと壁の間に空気の通り道がなくなり、カビにとって絶好の繁殖機会となってしまうため、注意が必要です。
また、日光が当たりにくい場所に設置するのも避けるべきです。桐たんすは呼吸する家具であるため、その周りの空気が常に循環している状態が理想です。風通しが悪く、空気がよどんでいる場所では、桐本来の調湿機能も十分に発揮されません。
カビのリスクを減らすためのもっとも簡単な対策は、桐たんすを壁から5〜10cmほど離して設置することです。たったこれだけで、たんすの裏側に空気が流れるようになり、湿気がこもるのを防げます。
住宅環境の変化
桐たんすが日本の家庭で広く使われてきた時代と現代とでは、私たちの住宅環境が大きく変化しました。このことも、カビが発生しやすくなった一因と考えられます。
かつての日本の木造家屋は、隙間が多く、風通しを重視した造りになっていました。そのため、室内でも自然な空気の循環があり、湿気がこもりにくかったのです。
一方、現代の住宅は、コンクリート造のマンションなど高気密・高断熱の家が主流です。こうした住まいは、冷暖房の効率が良いというメリットがある反面、空気の逃げ道が少なく、一度入り込んだ湿気が外に排出されにくいというデメリットも抱えています。そのため、意識的に換気を行わないと、室内全体の湿度が高くなりがちです。
このような住宅環境の変化は、本来湿気に強いはずの桐たんすにとっても、非常に過酷なものとなっています。昔の家と同じ感覚でいると、気づかぬうちにカビを発生させてしまう可能性があります。
自分でできる桐たんすのカビ取り方法(軽度)

桐たんすの表面に、うっすらと白い綿のようなカビを見つけて、ドキッとした方もいるかもしれません。でも、慌てることはありません。ごく初期の段階であれば、自分でお手入れが可能です。
軽度のカビなら、乾いた柔らかい布を使って表面のホコリや汚れを乾拭きし、目に見える汚れを取り除くことが基本です。表面のホコリや汚れと一緒に、発生したばかりの軽いカビなら取り除けることがあります。
このとき避けてほしいのが、水拭きです。良かれと思ってやりがちなのですが、木材に水分が残ってしまい、かえってカビが喜ぶ環境を作ってしまいます。
この乾拭きで対処できるのは、ごく表面的なカビに限られます。拭き取っても黒っぽいシミが残っていたり、カビの臭いが消えなかったりする場合は、カビが奥に根を張っているサインかもしれません。
次に、こうした自分で対処が難しくなってくる中度〜重度のカビの状態について、詳しく見ていきましょう。
自分ではカビ取りが難しい桐たんすの状態(中度〜重度)

乾拭きで取れないカビは、状態が進行しているサインです。桐材の内部まで菌が侵食したり、黒いシミになったりしていると、自分で対処することは難しくなります。
ここでは、プロへの相談を検討すべき状態について解説します。
カビの菌が桐材の内部まで侵食している
表面を乾拭きしても、黒い点々やシミのようなものが残ってしまう…。それは、カビの菌が表面だけでなく、桐材の内部にまで広がっている証拠です。
表面に見えるカビを拭き取っても、内部に残っている菌が再び表面に現れ、繰り返し発生してしまいます。このように、一度内部まで侵食してしまうと、表面を拭くだけでは菌を取り除くことはできず、根本的な解決にはなりません。
かといって自分で無理に削ろうとすると、均一にできずムラになったり、たんす本来の美しい風合いを損ねたりする恐れがあります。ここまでくると、なるべく早い段階で専門家に相談するのが良いでしょう。
内部の削れない部分にカビが発生
桐たんすの構造上、引き出しの隙間や底板の裏側など、手が届きにくい部分にカビが生えることがあります。こうした箇所は目視で確認しにくく、気づいたときには被害が広がっているケースも少なくありません。
削り直しができる表面部分と違い、内部の部材は簡単に取り替えられないことが多いため、家庭での処置は難航します。無理に取り除こうとすると、家具自体を傷める危険もあります。
そのため、内部に広がったカビは業者による分解や専門的な洗浄に頼るしかありません。放置しておくと収納している着物や洋服にまで悪影響を及ぼすため、早めの対応が求められます。
古い桐たんす、カビ取り後に考えられる活用・処理方法

カビ取りをして綺麗になったたんすを前に、これからの使い方を考える方も多いのではないでしょうか。美しくリメイクしたり、専門業者に買い取ってもらったり。たんすの新たな未来を一緒に考えてみましょう。
プロに依頼してリメイクする
カビは取れたけれど、長年ついていたシミや傷はやっぱり気になる…。そんなふうに感じていませんか?プロのリメイクなら、そんなお悩みも解決できます。
リメイクは、ただ綺麗にするだけでなく、今の暮らしに合わせて作り変えることができるのも大きな魅力です。取っ手の金具をモダンなデザインに変えたり、お部屋の雰囲気に合わせて色を塗り替えたり。思い出の品を、新しい姿でこれからも使い続けることができます。
両親から受け継いだものなど、愛着があってどうしても手放したくない方にとって、リメイクは一番心温まる選択肢かもしれません。
専門業者に買取を依頼する
カビ取りという手間をかけた桐たんすだからこそ、このまま眠らせておくのは少し惜しいものですよね。そのたんすには、専門業者が見出す新たな価値が眠っているかもしれません。自分で綺麗にお手入れしたそのひと手間も、決して無駄にはなりません。
買取なら、処分費用がかからないどころか、思わぬ収入になることも。それに、もし桐たんす自体に値段がつかなかったとしても、諦めるのはまだ早いかもしれません。多くの場合、専門業者は着物や骨董品なども扱っているため、他の不用品を一緒に売ることで、たんすの処分費用をまかなえる可能性もあるのです。
桐たんすの査定をきっかけに、家の中に眠っていたものの価値に気づける。それも、買取を試してみる大きな意味といえるでしょう。
「これからの管理を考えると少し気が重い…」そう感じているなら、たんすがきれいなうちに、一度気軽に相談してみてはいかがでしょうか。
正しい方法で処分する
愛着ある桐たんすですが、リメイクして使い続けることも、誰かに買い取ってもらうことも難しい…と、結論に至ることもあると思います。その際に考えるのが、最終的な選択肢としての処分です。
まず、お住まいの自治体に連絡し、粗大ゴミとして回収してもらう方法があります。その場合、手数料がかかるほか、指定の場所まで自分で運び出す手間も考えなくてはなりません。不用品回収業者に依頼して、家から運び出してもらう方法もありますが、こちらも費用が必要です。
処分には、どうしても手間や費用がかかってしまいます。ですが、それは桐たんすとの思い出をきちんと整理し、あなたの暮らしを前に進めるための過程でもあります。
最後まで責任をもって、後悔のないよう、正しい方法で手放してあげましょう。
たんすの処分方法については、下記の記事が役立ちます。
✅️ 合わせて読みたい:たんす処分のポイントと注意点を徹底解説!費用を抑えて損しない方法
桐たんす買取のコツ

桐たんすの買取を決めたなら、知っておきたいコツがあります。少しの工夫で買取価格が変わることも。大切な家具の価値を正しく評価してもらうために、押さえておきたいポイントを紹介します。
桐たんすの買取実績が豊富な業者を選ぶ
桐たんすは、ただの古い家具ではありません。素材や作られた年代、職人の技術など、その価値を正しく判断するには専門的な知識が必要です。そのため、どんなものでも買い取るリサイクルショップではなく、桐たんすの買取実績が豊富な買取の専門業者を選びましょう。
業者の公式サイトなどを見て、桐たんすの買取事例が紹介されているかを確認してみてください。実績が多い業者は、桐たんすの価値をよく理解しているだけでなく、修理して再び販売するルートも持っています。
できる範囲で状態を整えておく
桐たんすを売却する前には、軽く乾拭きをしてホコリや汚れを取り除いておくと印象が良くなります。専門的な修復までは不要ですが、査定時に清潔に見えるだけでも評価が変わることがあります。
ただし、前述の通り、水拭きや薬剤の使用は木材を傷める可能性があるため避けましょう。無理のない範囲でできるケアにとどめるのが安心です。
丁寧に扱われてきたと感じられる状態で査定に出すことは、業者にとってもプラス材料となり、少しでも高い評価につながります。
まとめ売りしやすいか確認する
もし桐たんすの他にも、手放そうか迷っている着物や帯、骨董品などがあれば、一緒に査定してもらえるか確認してみるのがおすすめです。多くの場合、骨董品や古家具の買取業者は、幅広いジャンルの品物を取り扱っています。
そのメリットは、もし桐たんす自体にあまり値段がつかなかったとしても、他の品物と合わせることで、全体としてまとまった買取額になりやすいことです。たんすの処分費用を、他の品物の買取額でまかなえる、といったケースも少なくありません。
あちこちの業者に連絡する手間も省けますし、一度に家の整理が進むのも助かります。桐たんすをきっかけに、家の中に眠っているものの価値を見直す良い機会になるかもしれません。
出張買取を利用する
桐たんすは、とても大きくて重い家具。自分で店頭まで運ぼうとすると、たんすや家を傷つけてしまったり、体を痛めてしまったりする危険が伴います。そこでぜひ利用したいのが、専門家が自宅まで査定に来てくれる出張買取です。
出張買取は、家具や骨董品の買取では一般的な方法で、多くの専門業者が無料で対応してくれます。電話や公式サイトから申し込むだけで、約束の日時に査定士が訪問してくれるので、手間がかからず、とても便利です。
自宅にいながら、安全かつ安心して査定を任せられるのが大きな魅力です。もし買取が成立すれば、その後の運び出しも業者が専門のスタッフと一緒に行ってくれるので、最後まで心配は無用です。
劣化しないうちに売却する
桐たんすは長く保管できる家具ですが、放置すればカビや変色が進み、査定額は下がってしまいます。状態が良いうちに売却することが、高値で取引するための基本です。
特に湿気の多い環境に置かれていると、劣化の進行は早まります。使わないと判断した時点で早めに業者へ相談するのが賢明です。
「もう少し後で」と先延ばしにすると価値が下がることもあるため、売ると決めたらタイミングを逃さず動くことが肝心です。
まとめ
桐たんすにカビが生えたら、まずは乾拭きなどの基本的なケアで対応できるかを確認してみましょう。表面にとどまる軽度のカビであれば、自分で対処することも可能です。
一方で、黒ずみや内部に広がるカビは自分では取り除けません。その場合は、プロによる修理やリメイクを検討することになります。
そして、保管や手入れが難しいと感じるなら、買取を活用するのもおすすめです。業者選びや査定前の準備といったコツを押さえることで、納得のいく手放し方ができるでしょう。