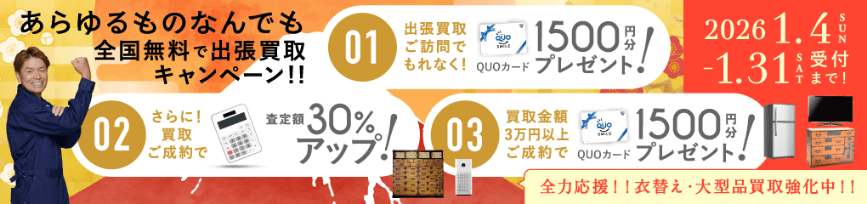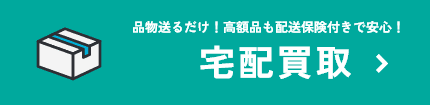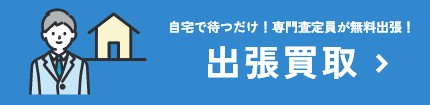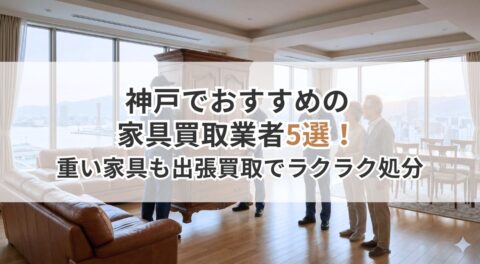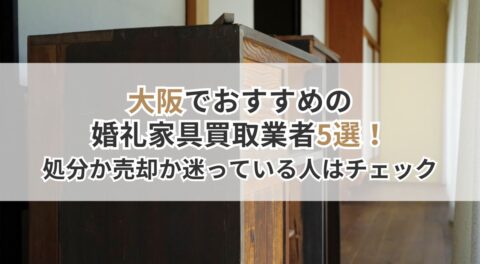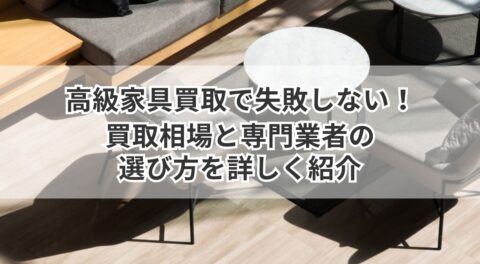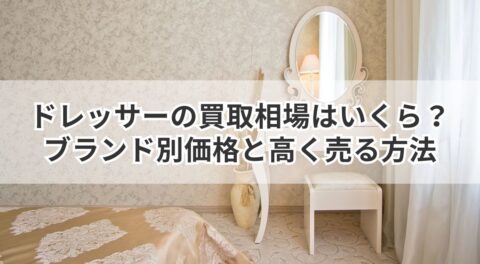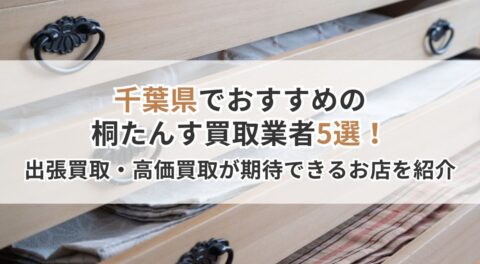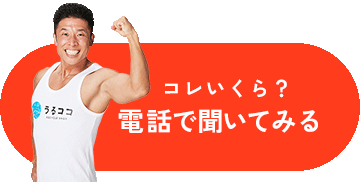桐たんすのデメリットとは?【購入&所有者向け】手入れ・置き場所・処分の後悔しないために
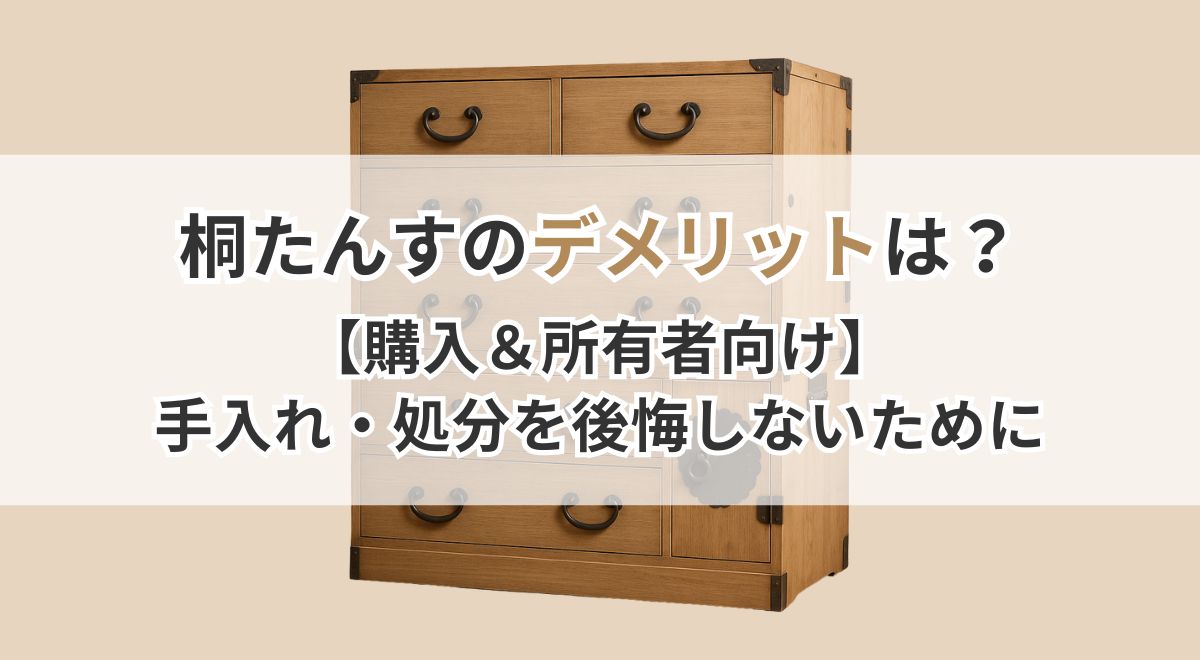
桐たんすは、高品質で一生使える良い家具。でも「傷つきやすくて手入れが大変そう」「現代のインテリアに合わない」など、気になるデメリットも多いですよね。親から受け継いだものの、置き場所に困っている方もいるかもしれません。
しかし、デメリットを正しく理解し、対策を知れば、桐たんすは最高の収納家具になります。
本記事では、購入前に知るべき注意点から、所有者が抱えるカビや置き場所の悩み、そして不要になったときの対応策まで、分かりやすくまとめています。
扱いづらさを感じている方も、あらためて桐たんすの価値を見直すきっかけになるはずです。
【購入前に知るべき】桐たんすの5つのデメリット

高品質な桐たんすは、衣類を永く大切に保管できる家具です。しかし、その一方で、素材の特性からくるいくつかの注意点をはじめ、デメリットと呼ぶべき点もあります。
ここでは、購入前に知っておくべき5つのデメリットと、その対策について解説します。
傷がつきやすい
桐たんすの素材である桐材は、高い調湿効果を持つ一方、非常に柔らかく、物理的な衝撃で傷やへこみがつきやすいのがデメリットです。掃除機をぶつけたり、硬い物を落としたりすると、すぐに跡が残ることがあります。
そのため、たんすの上には物を置かない、頻繁に物の出し入れをする場所の近くは避ける、といった配慮が求められます。日々の生活の中で、少し丁寧な扱いを心がけることが大切です。
ただし、このデリケートさは修理がしやすいという利点の裏返しでもあります。小さな傷は味わいとなり、大きな傷も専門業者による削り直しで美しく再生ができます。
黒く変色しやすい
桐たんすは時間の経過により、表面が黒っぽく変色することがあります。これは桐材のタンニン成分が空気と反応することで起こる自然な現象ですが、見た目の美しさを損なうため、デメリットと感じる方は多いでしょう。
この変色を避けるには、設置環境に工夫が必要です。湿気がこもりやすい壁際や直射日光が当たる場所は避けてください。
変色が味になるとも言われますが、購入当初の見た目を保ちたい方にとっては、やや扱いづらい面もあるかもしれません。
価格が高い
職人が手掛けた本格的な桐たんすは、量販店の家具と比べて高価であり、購入のハードルとなるのは事実です。しかし、その価格は、厳選された素材と高度な技術に裏打ちされています。
数年で買い替える家具とは違い、修理しながら一生涯、あるいは次の世代まで使える「資産」としての価値を持っています。長期的に見れば、そのコストパフォーマンスは決して悪くありません。
それでも、もし新品の価格が高いと感じるなら、状態の良い中古品や、リメイクされた再生品を選ぶことで、費用を抑えつつ桐たんすのある暮らしを始められるでしょう。
設置場所が限定される
桐たんすの優れた調湿性を活かし、デリケートな素材を守るためには、設置場所への配慮が必要です。この置き場所を選ぶというのが、デメリットと感じられることがあります。
前述したように、直射日光や湿気が多い壁際に桐たんすを設置するのは、変色の原因となるため望ましくありません。また、エアコンの風が直接当たる場所も、木の反りの原因となるため避けるべきです。
壁から5cmほど離し、風通しを確保できる場所に設置するのが基本です。購入前には、こうした条件を満たす設置スペースが自宅にあるかを確認しておく必要があります。
場所をとる
伝統的な桐たんすはサイズが大きく、現代のコンパクトな住宅では圧迫感を与えることがあります。十分なスペースがなければ、部屋が狭く感じてしまうというデメリットです。
昔ながらの広々とした和室であれば問題ありませんが、限られたリビングや寝室に置く場合は、その大きさがネックとなるかもしれません。
ただし、近年では現代の住環境に合わせた、モダンでコンパクトな桐たんすも数多く作られているため、さまざまなタイプの中から選べます。
【所有者向け】桐たんすを使い続ける上での課題

受け継いだり、長年愛用したりしている桐たんす。大切に使い続けたいと思う一方で、さまざまな課題に直面することもあるでしょう。ここでは、既に桐たんすを所有している方が抱えやすい3つの悩みと、解決策を紹介します。
カビや黒ずみが発生してしまったら
桐たんすの表面にポツポツとした黒い点や、全体的な黒ずみが発生した場合、その多くは湿気が原因のカビです。見つけたら、まずは柔らかい布で乾拭きし、決して濡れ雑巾や化学薬品を使わないでください。
初期の軽いカビであれば、桐たんすによって、消毒用エタノールを布に少量含ませて優しく拭き取り、よく乾燥させて対処できる場合もありますが、素人が行うのは望ましくありません。
根本的な解決や、広範囲に及んだ黒ずみには、専門業者による修復作業が最も確実な方法です。
引越しや模様替えで移動させたい
桐たんすは繊細な素材でできているため、引越しや模様替えの際は注意が必要です。まず、収納物はあらかじめ全て取り出し、引き出しが抜け落ちないようにしておきます。
梱包する際は、油分のないきれいな紙で全体を包んだあと、毛布などで保護すると安心です。テープを直接貼ると表面の「とのこ」が剥がれてしまうおそれがあるため、固定には直接触れない方法を選ぶようにしましょう。
移動時は、大人2人以上で運んでください。引きずったり、勢いよく置いたりすると床にキズが入るだけでなく、本体にも負担がかかります。
現代の住まいに調和させるには
和風の佇まいを持つ桐たんすを、フローリングの洋室やモダンな内装に合わせるのは難しい、と感じるかもしれません。しかし、いくつかポイントを意識すれば、お洒落なアクセントとして空間に調和させることもできます。
例えば、周りにはあまり家具を置かず、桐たんすを部屋の主役として際立たせる方法がありますたんすの上にモダンなデザインの花瓶やアートを飾ったり、間接照明を当てて木目の美しさを強調したりするのも効果的です。
あえて異素材のラグを敷くなど、他のインテリアとの組み合わせを工夫することで、桐たんすは「古い家具」から「個性的なインテリア」へと生まれ変わります。
桐たんすが持つメリットも再確認

ここまで桐たんすのデメリットや課題を中心に見てきましたが、あらためて長年愛されてきた理由についてもおさらいしておきましょう。
高い調湿効果で衣類を湿気から守る
桐材は、内部に微細な空洞を多く含む、まるで呼吸するかのような木材です。湿度の高い時期には、その空洞が空気中の湿気を吸収し、乾燥する時期には湿気を放出します。
この天然の調湿効果により、たんすの内部は常に一定の湿度に保たれます。
この働きが、湿気に弱い絹製品である着物や、カビが生えやすい衣類にとって、最高の保管環境を作り出します。日本の四季の変化から、大切な衣類を自動で守ってくれるのです。
桐成分による優れた防虫効果
桐の木には、タンニンやパウロニンといった、虫が嫌う天然の成分が豊富に含まれています。これらの成分が、衣類を食べる害虫を寄せ付けないため、防虫剤を入れなくても、大切な衣類を虫食いから守ることができます。
化学的な防虫剤を使わずに済むため、衣類に臭いが移る心配もなく、人や環境にも優しいのが魅力です。
デリケートな着物や高級なカシミヤ製品などの保管には、これ以上ないほど適しています。
火事に強い高い耐火性
「桐は火に強い」という事実は、昔からよく知られています。桐材は発火点が高く、熱伝導率も低いため、他の木材に比べて燃えにくいという性質を持っているのです。
また、火気にさらされると、表面が燃えて炭化層を作り、それが断熱材として働くため、内部への火の進行を遅らせます。
さらに、湿気を吸った桐が膨張して引き出しの隙間を塞ぎ、中に炎や水が入り込むのを防ぐともいわれています。金庫と同じように、大切な財産を災害から守る役割も果たしてきたのです。
親子三代にわたって使える耐久性
桐たんすは非常に軽くて柔らかい素材でありながら、大切に扱えば数十年〜百年単位で使える耐久性を備えています。経年によって味わいが増し、長く愛用できる点が醍醐味です。
実際に、親の代、祖父母の代から受け継いだ桐たんすを今でも使い続けている家庭も多く見られます。使い込まれたたんすには、思い出や暮らしの歴史が刻まれていくでしょう。
丁寧に使えば使うほど価値が増す家具として、桐たんすは使い捨てではない豊かさを感じさせてくれます。今の暮らしに、あえて取り入れる価値のある存在です。
桐たんすが不要な場合「捨てる」は最後の手段

さまざまな事情から、桐たんすを手放さなければならないこともあるかもしれません。でも、職人の手仕事が光る桐たんすを、いきなり「粗大ごみ」として捨ててしまうのは、あまりにも惜しい話です。
処分を決める前に、ぜひ考えてみてほしいのがリメイクと買取です。そして、どうしても手放す必要があるときの処分方法についても、最後に紹介します。
美しくリメイクする
長年の使用で付いた傷や黒ずみは、専門業者に依頼すれば、まるで新品同様に蘇らせることができます。桐たんすは「削り直し」を施し、表面を薄く削って再塗装することで、桐本来の美しい木肌を取り戻せるのです。
そして、ただ綺麗にするだけでなく、現代の住まいに合わせてリメイクすることもできます。
例えば、背の高い和だんすを、上下に分割して2つのチェストに作り変えたり、金具をモダンなデザインのものに交換したりと、あるいはオイル塗装をしたりと、今の暮らしに合った形に生まれ変わらせることができます。
費用はかかりますが、思い出の家具をこれからも使い続けたいと考える方にとっては、最も価値のある選択肢といえるでしょう。
専門の買取業者に高く買い取ってもらう
「もう使わないけれど、捨てるのは忍びない」というときは、専門の買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。桐たんすは、中古家具としての価値があり、古いものでも思わぬ高値がつくことがあります。
特に、有名産地(新潟県の加茂桐たんすなど)のものや、著名な職人の銘が入っているもの、凝ったデザインの金具が使われているものなどは、高額査定が期待できます。
傷や汚れがあっても、修復可能なため、買い取ってもらえるケースは少なくありません。
桐たんすの高価買取ポイントや業者の選び方については、下記の記事を参照してください。処分方法にも言及しています。
✅️ 合わせて読みたい:大阪でおすすめの桐たんす買取業者9選を紹介
どうしても処分する場合
リメイクや買取が難しい、あるいはさまざまな事情でどうしても処分せざるを得ない場合は、自治体のルールに従って適切に処分する必要があります。
桐たんすは粗大ごみに分類されるため、お住まいの自治体のウェブサイトなどで、申し込み方法や手数料を確認しましょう。
自分で指定の場所まで運び出すのが困難なら、民間の不用品回収業者に依頼する方法もあります。業者によっては高額な費用を請求されるケースもあるため、複数の業者から見積もりを取り、信頼できる業者を慎重に選んでください。
まとめ
本記事では、桐たんすのデメリットと、長く愛用するための知識を解説しました。傷つきやすさやデザインなど、注意点はありますが、どれも対策可能なものばかりです。
手入れや修理をすれば世代を超えて使える、サステナブルな伝統家具の価値を再発見できたのではないでしょうか。
それでもやはり、自宅で使い続けるのが難しいという場合には、「処分」を考える前に、一度専門の買取業者に相談してみるのがおすすめです。丁寧に作られた質の高い桐たんすであれば、思いがけず良い値がつくこともあります。
うるココでも桐たんす買取を行っていますので、お気軽にお声がけください。