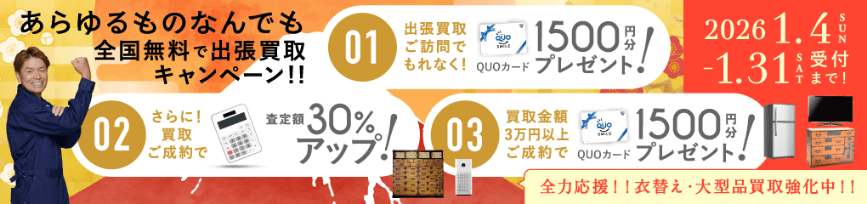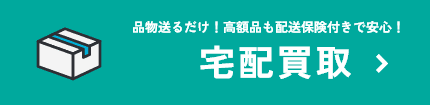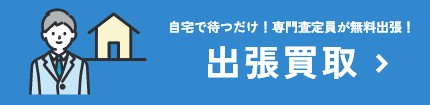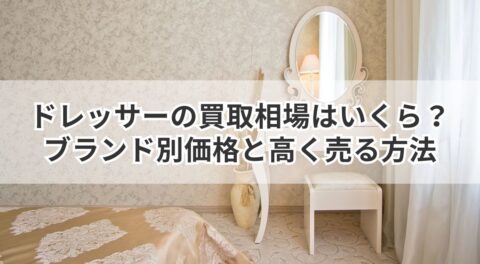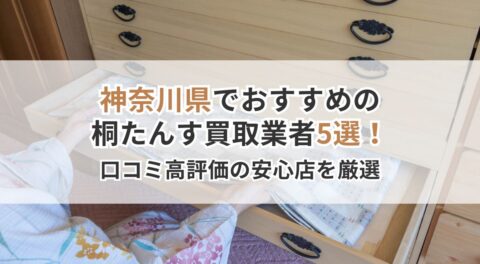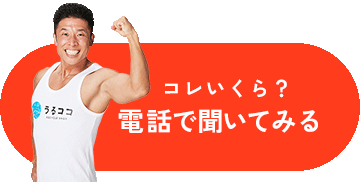桐たんすの着物しまい方|カビ・シワを防ぐ方法と管理が大変なときの対処法
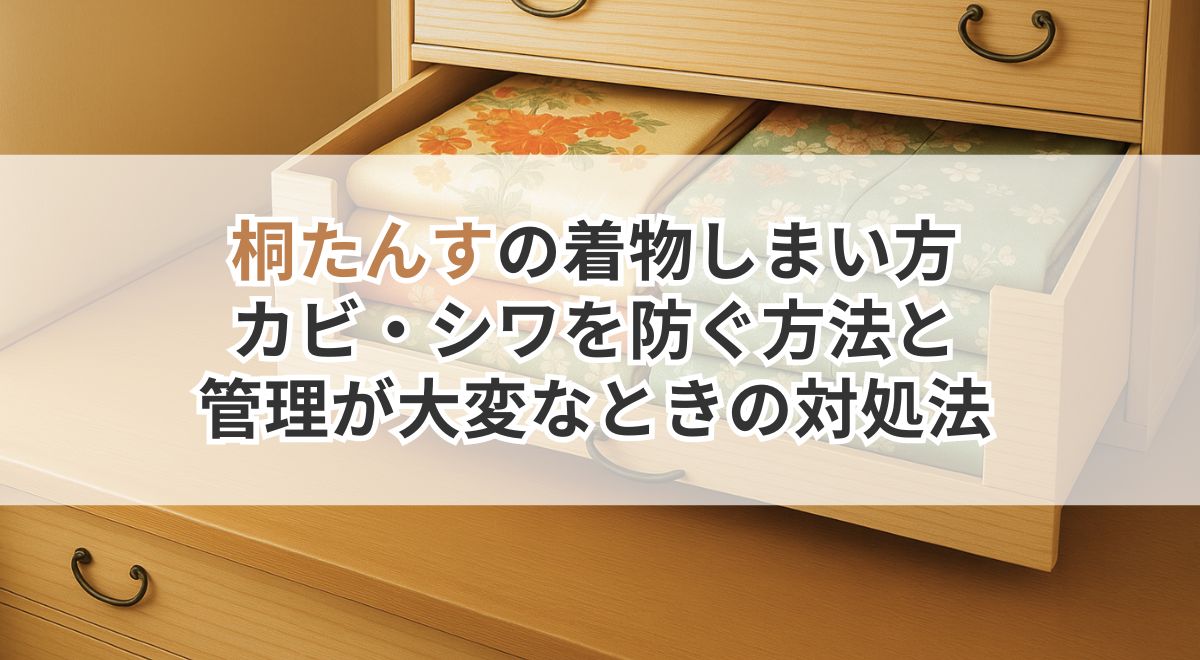
成人式や結婚式で活躍してくれた大切な着物。楽しい思い出とともにたんすへ戻すとき、「自己流でたたんだら、次に広げたときにシワだらけだった…」なんて経験は避けたいですよね。
この記事では、桐たんすに着物をしまう正しい手順を紹介します。なぜ桐たんすが着物保管に適しているのか、その理由も分かりやすく解説しました。
将来的に管理が大変になったときは、思い切って買取を選ぶのもひとつの方法です。大切に保管するか、新しい持ち主へ受け渡すか。その両方を知っておくことで、着物との向き合い方がぐっと広がります。
シワにならない!桐たんすの着物しまい方

大切な着物、いつまでも美しい状態で保ちたいものですよね。そのためには、着終わった後、たんすにしまう時のひと手間がとても大切になります。シワやカビ、変色から着物を守るための正しいしまい方を、4つのステップで解説します。
ステップ 1:収納前の準備
着用後の着物には、目に見えない汗や湿気が残っていますが、それだけでなく、小さなシミや汚れが付いていることもあります。まずは、着物全体を広げて、汚れやシミがないかを確認しましょう。もし汚れを見つけたら、無理に自分で対処せず、専門店に相談するのが安心です。
その後、風通しの良い日陰で半日〜1日ほど陰干しをしましょう。着物用のハンガーにかけ、湿気をしっかりと飛ばしてあげます。このひと手間で、カビのリスクをぐっと減らすことができます。
同時に、しまう場所である桐たんすの中も確認しておきましょう。引き出しを開けて空気を入れ替え、乾いた布で軽く拭いておきます。
ステップ 2:着物を「本だたみ」で正しくたたむ
着物の基本的なたたみ方は「本だたみ」と呼ばれる方法です。形に沿って丁寧にたたむことで、無理な折れやシワを防ぎ、長期保管に適した状態を作れます。
本だたみでは、裾や袖の形を整えながら縦に折り、全体を均一に重ねていきます。慣れないうちは少し難しく感じるかもしれませんが、一度覚えてしまえばスムーズに行えるようになるでしょう。
このたたみ方をすることで、余計なシワがつくのを防ぎ、桐たんすの引き出しにもすっきりと収まります。次に着る時も、さっと広げるだけで美しい状態を保てるはずです。
ステップ 3:新しい「たとう紙」で優しく包む
正しくたたんだ着物は、「たとう紙(たとうし)」で優しく包んであげましょう。たとう紙は、着物を湿気やホコリから守り、金箔や刺繍が他の着物と擦れるのを防いでくれる、着物にとっての布団のような存在です。
このとき、古くから使っている黄色っぽいものではなく、新しいたとう紙を使うのがおすすめです。古いたとう紙は湿気を吸う力が弱まっているだけでなく、シミの原因になることも。黄ばみやシワが目立ってきたら、交換のサインです。
着物が中でずれたり、シワになったりしないよう、中心にまっすぐ置いて丁寧に包みます。このひと手間が、たんすの中で着物を優しく守り、美しい状態を保つ秘訣なのです。
たとう紙のメリットや種類、使い方については下記の記事も参考にしてください。
✅️ 合わせて読みたい:たとう紙とは?メリットや種類、使い方などについて詳しく解説
ステップ 4:桐たんすへふんわり収納する
最後に、たとう紙で包んだ着物を桐たんすに収納します。このとき詰め込みすぎると通気性が悪くなり、シワやカビの原因となるため注意が必要です。
桐たんす自体が持つ調湿性や防虫効果は大きなメリットですが、それを活かすには収納の工夫も欠かせません。衣類同士が押し合わない程度にふんわりと置くことで、シワを防ぎながら快適な環境を作れます。
また、定期的に引き出しを開けて風を通すことも大切です。収納方法と日常的なケアを組み合わせることで、着物は長く美しいまま保たれます。
そもそも、なぜ着物をしまうのに桐たんすが最適なの?

昔から「着物の保管には桐たんす」と言われますが、その理由を詳しくご存知でしょうか。桐という木が持つ素晴らしい力と、着物を守るために考え抜かれたその造り。そこには、日本の気候と文化に寄り添う、先人たちの知恵が詰まっています。
その理由を6つにまとめたので、一つひとつ見ていきましょう。
優れた調湿作用
桐たんすには、まるで呼吸をするかのように湿度を調整してくれる調湿作用があります。湿気の多い夏には空気中の水分を吸い込み、乾燥する冬には水分を放出することで、たんす内部の湿度を一定に保とうとしてくれるのです。
この働きのおかげで、湿気に弱い絹でできた着物を、1年を通して最適な環境で保管することができるのです。カビや縮みから着物を守ってくれる、天然の除湿・加湿器のような役割を果たしてくれます。
プラスチックの衣装ケースにはない、この桐ならではの呼吸能力こそが、桐たんすが着物の保管に最適といわれる最大の理由ともいえるでしょう。
桐たんすのカビ取りについて扱った記事もあるので、ぜひ参考にしてください。
✅️ 合わせて読みたい:桐たんすのカビ、自分で取れる?進行度ごとの対策と買取など別の選択肢も紹介
天然の防虫効果
桐の木には、タンニンやパウロニンといった虫が嫌う成分が含まれています。そのため、衣類を食べる虫を寄せ付けにくいという、優れた防虫効果を持っています。
大切な着物を保管するのに、強い化学的な防虫剤をたくさん使うのは少し心配です。しかし、桐たんすであれば、それ自体が防虫効果を持っているため、余計な防虫剤を減らすことができるのです。
着物にも人にも優しい、天然の防虫効果。これも、デリケートな着物を保管する上で、桐たんすが選ばれ続ける大きな理由のひとつです。
高い密閉性
質の良い桐たんすは、職人の手仕事によって、引き出しや扉が隙間なくぴったりと閉まるように作られています。この精巧な造りが、高い密閉性を生み出しているのです。
引き出しをひとつ閉めると、空気が押し出されて隣の引き出しが少し開く、という話を聞いたことはありませんか?それは、たんすの密閉性が非常に高い証拠です。
この高い密閉性のおかげで、外の湿った空気やホコリが内部に入り込むのを防ぎ、桐の持つ調湿作用や防虫効果をさらに高めてくれます。
着物専用の設計
桐たんすは着物を収納することを前提に作られており、引き出しの大きさや深さも着物に適しています。たとう紙に包んだ着物を無理なく収められるため、折りジワや型崩れを防げます。
洋服用の収納家具に比べると、着物の大きさや形に合わせた設計であることは大きなメリットです。収納後に余分なスペースが少なく、すっきりと収まるのも安心できるポイントです。
着物に特化した設計だからこそ、長く大切に受け継がれてきた理由が理解できます。
火災・水害への耐性
桐は、他の木材に比べて燃えにくいという性質を持っています。発火点は425℃と高く、杉が240℃であることと比較してもよく分かります。そのため、桐は火にさらされても表面が焦げるだけで、なかなか中まで火が通りません。
また、水に濡れると膨張して、引き出しの隙間をぴったりと塞ぎ、中に水が入り込むのを防ぐともいわれています。「火事の時は、桐たんすに水をかけろ」という昔からの言い伝えは、こうした桐の性質に基づいているのです。
万が一の災害時にも、中の大切な着物を守ってくれる。そんな頼もしさも、桐たんすが持つ隠れた能力です。
軽量で丈夫
桐たんすは、そのしっかりとした見た目に反して、持ってみると驚くほど軽いことが分かります。桐は日本でとれる木材の中でも1番軽いとされ、世界の木材と比較してもバルサ材に次いで2番目に軽い木材なのです。
昔の家では、掃除や模様替えの際に、たんすを動かすことも多かったでしょう。この軽さはとても重宝されたはずです。
軽いだけでなく、割れや狂いも少ない丈夫な木材であることも、桐の素晴らしいところ。扱いやすく、かつ長く使える。実用性の高さも、桐たんすが愛され続ける理由です。
間違えると逆効果?防虫剤・除湿剤の正しい選び方

桐たんすには元々、着物を守る力が備わっていますが、より万全を期すために防虫剤や除湿剤を使いたい、と感じることもありますよね。ただし、これらは選び方と使い方を間違えると、かえって着物を傷めてしまうことがあるので注意が必要です。
まず、防虫剤は必ず「着物用」と書かれたものを選びましょう。
次に注意したいのが、種類の違う防虫剤を併用しないことです。例えば、樟脳(しょうのう)とナフタリンなど、成分の違うものを一緒に入れると、化学反応で溶けて液体になり、着物に落ちてしまうことがあります。これが、シミの原因になってしまうのです。新しいものを入れる際は、必ず古いものを取り出してからにしてください。
防虫剤は、着物に直接触れないよう、たとう紙の隅の方に置くのが基本です。また、除湿剤を置く場合も、水がたまるタイプのものは避けましょう。万が一倒れたり漏れたりした際に大変なので、引き出し用のシートタイプのものを選ぶと安心で。
桐たんすへの着物のしまい方は分かったけど…管理が大変なら

正しいしまい方を知ったものの「これをずっと続けていくのは、正直ちょっと大変かも」と感じた方もいるかもしれません。着物を着る機会が減ったり、ライフスタイルが変化したりすることもあるでしょう。
そこで、大切な着物や桐たんすの今後について、ゆっくり考えてみる良い機会かもしれません。ここでは、着物や桐たんすの扱いに迷ったときに考えたい選択肢を紹介します。
桐たんすや着物の今後を考えるタイミング
着物を着る機会がめっきり減ってしまった、虫干しなどのお手入れが時間的・体力的に難しくなってきた、親から譲り受けたものの自分では着ることがない…。さまざまな理由で、着物や桐たんすの管理を負担に感じ始めることがあります。
大切なものだからこそ、しまいっぱなしにして傷ませてしまうのは心苦しいものです。思い出の品が、「管理しなければならないもの」という重荷に変わってしまったら、それは今後について考えるタイミングといえます。
無理に持ち続けるのではなく、その価値を一番良い形で次に繋いであげる。それも、着物や桐たんすへの深い愛情の示し方のひとつです。
専門業者に着物を買い取ってもらう
「もう自分では着ないけれど、このまま眠らせておくのはもったいない」。そう感じている着物があるなら、その価値を正しく評価してくれる専門業者に買い取ってもらう、という方法があります。
専門業者に託せば、大切にしてきた着物を、次に必要としている誰かのもとへ届けてくれます。たんすの収納スペースに余裕が生まれるだけでなく、思わぬ収入になる可能性があるのも嬉しいですよね。
思い出の詰まった着物が、誰かの新しい思い出を作るために旅立っていく。そう考えると、手放すことも、とても前向きな選択肢に思えませんか。
場所をとる桐たんすも一緒に買い取ってもらう
着物を手放した後、次に考えるのが「この大きな桐たんすをどうしよう?」ということではないでしょうか。着物がないのであれば、場所をとる桐たんすも不要になってしまうケースは少なくありません。
着物の買取業者の多くは、桐たんすの買取も専門的に行っています。着物と一緒に査定を依頼すれば、一度の手間で、両方をまとめて手放すことができます。
一つひとつ別の業者を探したり、処分の手続きをしたりする手間が省け、とても効率的です。着物と桐たんす、両方の価値をしっかりと見てもらい、部屋も心もすっきりと整理する。そんな一石二鳥の選択肢も、ぜひ検討してみてください。
まとめ
この記事では、大切な着物をシワやカビから守るためのしまい方を、準備から収納までの4ステップで解説しました。
しまい方を学んだ上で、お手入れが難しいと感じたり、着る機会が減ったりした場合には、無理に持ち続けるのは得策ではありません 。専門業者に買い取ってもらい、次に大切にしてくれる方へ繋ぐことも、素晴らしい選択肢のひとつです。
「うるココ」では、着物や桐たんすの価値を丁寧に見させていただきます。もし手放すことをお考えでしたら、ぜひ一度、桐たんす買取についてご相談ください。