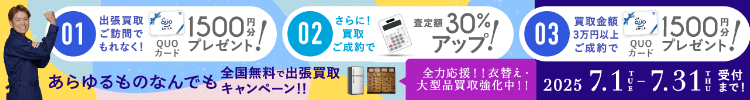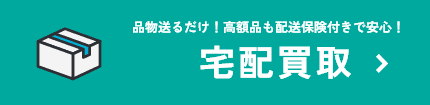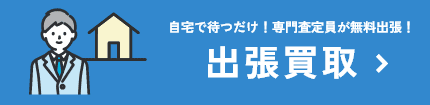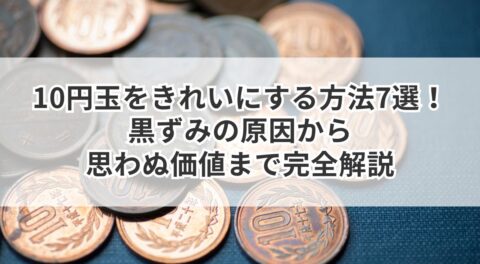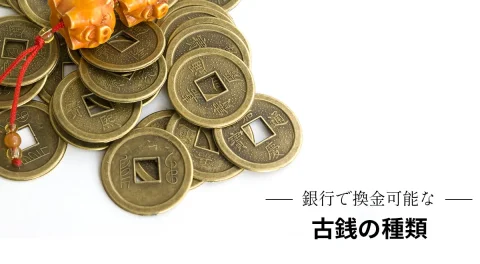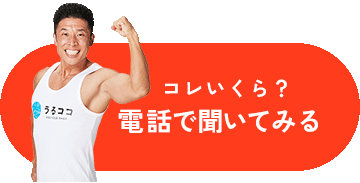昭和のお金の価値とは

現在でも昭和に発行されたお金は、流通しています。財布の小銭入れを確認すれば、「昭和◯年」と刻まれている硬貨が見つかるかもしれません。
本記事では、昭和のお金で価値があるものについて紹介します。
昭和のお金一覧
まずは、昭和時代に発行されたお金の一覧を紹介します。
昭和は比較的最近であるため、買取相場はそれほど高いわけではありませんが、発行枚数や状態によっては高額となる場合もあります。
硬貨
大正時代のお金は、青銅貨や銀貨、金貨がありましたが、昭和の硬貨はより安価なアルミやニッケルが使用されるようになっています。
| 硬貨 | 発行年 |
|---|---|
| 菊10銭アルミ貨 | 1940年 |
| 富士1銭アルミ貨 | 1941年 |
| 5銭アルミ青銅貨 | 1938年 |
| 5銭アルミ貨 | 1940年 |
| 10銭アルミ青銅貨 | 1938年 |
| 10銭ニッケル貨 | 1933年 |
| 1銭錫貨 | 1944年 |
| 1銭アルミ貨 | 1938年 |
| 5円黄銅貨(国会議事堂・穴なし) | 1948~1949年 |
| 5円黄銅貨(稲穂等・楷書体) | 1949~1958年 |
| 10円青銅貨(平等院鳳凰堂・ギザあり) | 1951~1958年 |
| 50円ニッケル貨(菊・穴なし) | 1955~1958年 |
| 50円ニッケル貨(菊) | 1959~1966年 |
| 100円銀貨(鳳凰) | 1957~1958年 |
| 100円銀貨(鳳凰) | 1959~1966年 |
| 500円白銅貨(桐) | 1982~1999年 |
| 1円アルミニウム貨 | 1955年 |
| 5円黄銅貨 | 1959年 |
| 10円青銅貨 | 1959年 |
| 50円白銅貨 | 1967年 |
| 100円白銅貨 | 1967年 |
紙幣
昭和時代の紙幣は、現在発行されていないものの、使用できるものがあります。
これらの中には希少価値の高いものも存在します。
| 紙幣 | 発行年 |
|---|---|
| 日本銀行兌換券(50円・200円) | 1927年 |
| 兌換券(5円・10円・20円・100円・200円) | 1927~1946年 |
| 兌換券甲号 | 1942~1946年 |
| 改正兌換券(5円・200円) | 1942~1946年 |
| 不換紙幣(1円・5円・10円・100円) | 1943~1944年 |
| 改正不換紙幣(1円・5円・10円・100円) | 1944~1945年 |
| 再改正不換紙幣10円 | 1945年 |
| 政府紙幣(小額政府紙幣) | 1938~1948年 |
| 日本銀行券(5銭・10銭) | 1944~1953年 |
| 日本銀行券 い1円券(武内宿禰) | 1943年 |
| 日本銀行券A号1円券(二宮尊徳)・5円券(彩文模様)・10円券(国会議事堂)・100円券(聖徳太子) | 1946年 |
| 政府紙幣B号 | 1948~1958年 |
| 日本銀行券B号50円券(高橋是清)・100円券(板垣退助)・500円券(岩倉具視)・1000円券(聖徳太子) | 1950~1965年 |
| 日本銀行券C号500円券(岩倉具視)・1000円券(伊藤博文)・5000円券(聖徳太子)・1万円券(聖徳太子) | 1958~1986年 |
| 日本銀行券D号1000円券(夏目漱石)・2000円券(首里城)・5000円券(新渡戸稲造)・1万円券(福沢諭吉) | 1984~2007年 |
昭和前期で価値のあるお金

昭和前期は、大正時代から続いて
- 1銭
- 5銭
- 10銭
- 50銭
が製造されています。
硬貨によって素材やデザインは種類がいくつかあり、1銭は桐が刻印された青銅貨とカラスが刻印された黄銅貨がありました。
黄銅貨は昭和13年の間だけ発行されましたが、発行してすぐに戦争が起き、その影響で素材がアルミニウムに変わったのでレアといえます。
5銭は菊の刻印がある白銅貨、とびの刻印があるニッケル貨があります。
10銭は菊のデザインが中心の白銅貨やニッケル貨が発行されており、50銭は鳳凰や菊の文様で、素材には銀貨が使用されています。
銀を約72%含有する50銭銀貨は高品位で、銀貨の希少性もプラスされて価値が高くなりやすいです。
戦時中に発行されたお金は価値があまりない
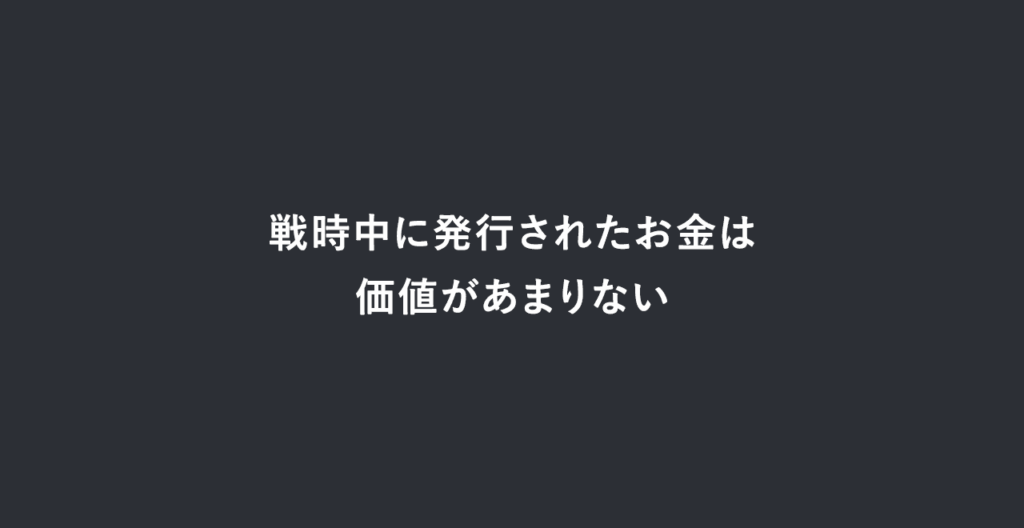
戦争中は硬貨はアルミニウムや錫を主体にして製造されました。
- 1銭→ カラス、富士、菊
- 5銭→ とび、菊
- 10銭→ 菊、桜、稲
などのデザインがありますが、戦時中の硬貨で価値が高いものはあまりありません。
戦争が終わってからも、1銭錫貨、5銭錫貨、10銭アルミ貨などといった、錫とアルミニウムで硬貨の製造が行われますが、それもGHQの規制で使えなくなり、その当時あった薬莢や弾帯のスクラップを使って黄銅貨が製造されました。
戦後のお金で価値のあるもの
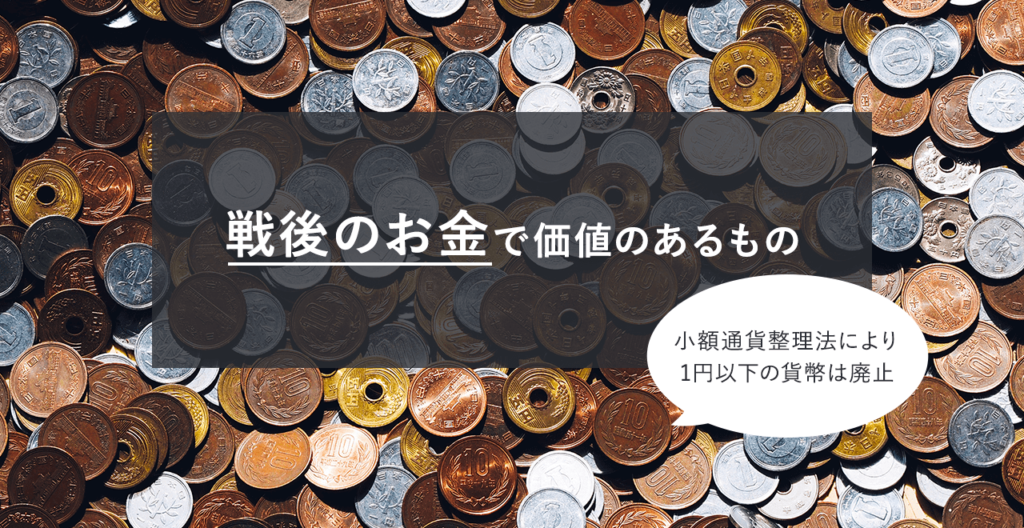
昭和28年の小額通貨整理法により、1円以下の貨幣は使われなくなりました。
この辺りから、今の貨幣に通じるようなデザインが作られ始め、5円銅貨はそれまで穴なしだったのが、今の稲デザインで穴あり硬貨になりました。
昭和28年に、今でも使われる10円青銅貨が製造され、昭和30年には1円アルミ貨が製造されました。
50円硬貨も、穴なしのニッケル貨から穴ありのニッケル貨に変更され、昭和42年になり、今と同じ穴ありの白銅貨に変更されました。
100円硬貨は、50円玉と同じ時期に銀から白銅貨に素材が変わります。
昭和57年に、500円玉が白銅貨として発行されますが、偽造を防止する目的もあり、平成12年にニッケル銅貨に変更されました。
100円銀貨や、流通した量が少ない硬貨、また純度が高い硬貨は、価値が高く高値になることがあります。
今あるお金で価値のあるもの

昭和後期に、今ある硬貨が揃うことになりますが、今も流通する硬貨は、製造年数で価値が違います。
製造量が少ない硬貨ほど、その価値が上がり、昭和製造のものでは、以下の硬貨の価値が高くなっています。
- 5円玉→ 昭和32年
- 10円玉→ 昭和32~34年
- 50円玉→ 昭和35年、昭和60~62年
- 100円玉→ 昭和36年、昭和39年
- 500円玉→ 昭和62年、昭和64年
財布の中にこれらの硬貨はありませんか?
まとめ
昭和のお金で価値があるものについて紹介しましたが、いかがでしたか。
昭和は、比較的であるため「もしかすると珍しいのでは?」という硬貨・紙幣をお持ちの人も、少なくないかもしれません。
そのようなときは、買取査定のご依頼をしてください。
うるココでは、古銭買取を行っています。お手持ちの古銭や古紙幣で価値が分からないものがあれば、査定させてもらいます。
思わぬ価値がつくこともあるため、もしや、というものがあればご用意しておいてください。